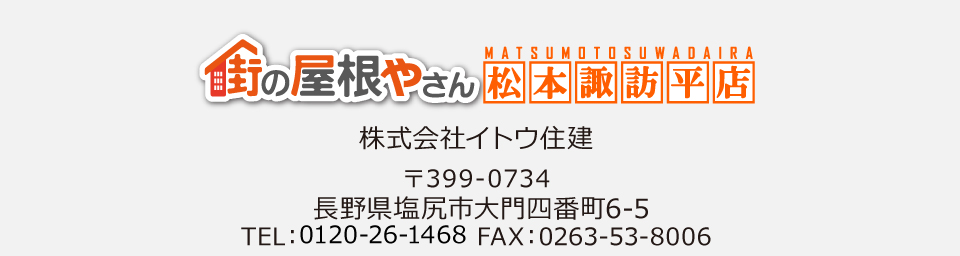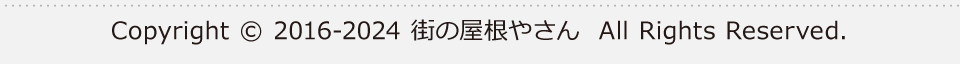2026.01.25
2026年1月26日 更新 太陽光屋根の不安 松本地区でも太陽光パネルを設置している住宅が増え、「この屋根、メンテナンスはどうするの?」というご相談をよくいただきます。屋根の上にパネルが載っていると、塗装できるのか、工事のたびに外す必要があるのか、不安になりますよね。実は、太陽光…
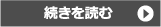

「天井にシミが広がってきて心配…」そんな不安から始まったK様邸の雨漏り調査。
前回の記事(調査編はこちら)では、棟板金の浮きやトタン屋根の劣化、コーキングの切れなど、複数の原因が見つかりました。
当初は「カバー工法(既存屋根の上に新しい屋根をかぶせる工法)」も検討しましたが、調査の結果、下地の傷みが深刻で、根本的な修繕が必要と判断。
今回は、K様邸で実際に行ったトタン屋根の葺き替え工事の様子を、現場の写真とともに詳しくお伝えします。
「葺き替えとカバー、どちらを選ぶべき?」と悩んでいる方にも、判断のヒントになるはずです!
K様邸は築30年以上の木造住宅。
2階と1階の屋根が段差で組み合わさった構造で、勾配が緩く水がたまりやすい形状でした。
前回の調査で見つかったのは、次のような症状です。
・トタン屋根のサビ・浮き・釘抜け
・棟板金のズレ
・コーキング(防水材)の劣化
・増築部の下地板の腐食
これらの症状から、「表面を覆うだけのカバー工法では再発の恐れがある」と判断し、
**屋根をすべて剥がして下地からやり直す“葺き替え工事”**に決定しました。
既存の屋根の上に新しい屋根材を重ねる工法。
メリットは「工期が短い」「廃材が少なくコストを抑えられる」こと。
一方、下地の傷みを直せないため、今回のように腐食がある場合は再発リスクが高まります。
古い屋根をすべて撤去し、下地(野地板)や防水シート(ルーフィング)を新しくしてから新しい屋根材を施工する方法。
初期費用はかかりますが、「耐久性」「断熱性」「雨漏り対策」のすべてを根本から改善できます。
K様邸では、今後20年以上安心できる屋根を目指し、葺き替えを選択しました。

一見すると全体の形はしっかりしているように見えますが、近づいてみると各所に経年劣化のサインが出ていました。
特に、トタンの表面のサビや釘の浮き、つなぎ目のコーキングのひび割れが多数確認され、雨水が侵入する可能性のある箇所が点在していました。
また、屋根の形状が2階・1階で段差があり、雨水の流れが複雑になっている点もリスク要因。
勾配が緩やかな部分では水が滞留しやすく、サビや腐食が進みやすい構造でした。
諏訪市は降雪量が多く、冬の雪解け水が屋根上に残りやすいため、こうした構造は雨漏りリスクが高いのです。
外観の状態から「部分補修では一時的な効果しか期待できない」と判断し、全体葺き替えの必要性を感じました。


古いトタン屋根を1枚ずつ丁寧に撤去していきます。
撤去の際には、トタンを固定していた釘やビスが錆びついていたり、部分的に浮いていたりすることが多く、職人が1つ1つ手作業で取り外しました。
下地が見えると、予想通り腐食と傷みが広範囲に進行しており、雨水の侵入経路が複数確認されました。
釘が効かなくなっていた箇所や、湿気による黒ずみ、カビの発生もありました。
この状態では、カバー工法では根本的な改善ができず、下地ごと交換する葺き替えが最適という結論に。
撤去作業は屋根全体の構造を再確認できる重要な工程であり、
「どの範囲で下地補強が必要か」「どの部分に雨水が集中していたか」を把握する大切なプロセスです。

既存のトタン屋根を撤去したところ、**下地として使われていたのが「トントン葺き」**でした。
「トントン葺き」とは、杉板や薄い板材を“トントン”と釘で打ち付けて並べていく昔ながらの工法で、戦後〜昭和期の住宅でよく見られます。
当時は施工が容易でコストも抑えられるため広く採用されていましたが、現在の基準から見ると防水性や強度が不十分で、長年の使用により板の隙間や釘穴から雨水が浸入しやすくなっていました。
実際に確認すると、トントン葺きの板の一部が黒ずみ、湿気と雨水の影響で腐食している箇所もありました。
また、板の継ぎ目が広がっていたり、釘の効きが甘くなっているところも多く、このまま上から屋根をかぶせても再び雨漏りが起きる可能性が高い状態。
職人の判断で、劣化したトントン葺きの上に新しい構造用合板を全面に敷いて補強する方針に切り替えました。
こうすることで、しっかりした強度と防水性を確保し、長持ちする屋根下地を実現します。

1階の増築部分をめくってみると、**ガラ板(厚みの薄い板)**が下地として使われていました。
ガラ板は軽量で施工が簡単な反面、耐久性や防水性に劣るため、経年劣化で割れや反りが生じ、釘が効かなくなることが多いです。
実際に確認すると、板の隙間から湿気がこもり、腐食やカビの発生がありました。
この状態では、上から新しい屋根材を載せても、しっかり固定できず将来的に雨漏りの再発リスクが高まります。
現場では、板の浮きや欠損を一つひとつチェックし、全面的な下地の張り替えを行う方針に切り替えました。

トントン葺きの杉板、ガラ板では心許ない下地だったので、12mm厚の構造用合板を新たに施工しました。
構造用合板は耐久性・強度に優れ、釘やビスがしっかり効くのが特徴。
屋根の荷重を均等に支えることができ、風・雪・地震にも強い安定した下地を形成します。
施工の際には、板の継ぎ目が一列に並ばないように千鳥張り(互い違い)に配置し、全体の剛性を高めました。
また、垂木(たるき)への固定も確実に行い、将来的なたわみや浮き上がりを防ぎます。
この補強により、これまで不安定だった屋根全体の構造がしっかりと安定し、
「上に乗ってもたわまない」安心の土台が完成しました。


続いて、屋根全体に防水シート(ルーフィング)を施工します。
ルーフィングは、屋根材の下に敷く第二の防水層で、雨水が屋根材の隙間から入り込んでも、下地を守ってくれる非常に重要な存在です。
施工のポイントは、
・水の流れを考えて下から上へと順番に張る
・重ね幅を100mm以上確保して雨の逆流を防ぐ
・釘穴からの漏水を防ぐため、丁寧なタッカー留めを行う
諏訪市のように雨・雪・結露の多い地域では、ルーフィングの品質が屋根寿命を左右します。
慎重に施工し、どの箇所にも隙間や浮きがないことを確認しました。

今回使用したのは、軟質弾性プラスティックルーフィング「チャンピオンルーフィング」。
一般的なアスファルトルーフィングに比べ、
・柔軟性が高く建物の動きに追従
・耐熱性・耐寒性が優れており、気温差でも劣化しにくい
・軽量で施工しやすく、接合部のシール性も高い
特に諏訪市のような寒暖差の大きい地域では、建物が季節ごとにわずかに動くため、
柔軟な素材のほうがひび割れにくく、防水性能を長期間維持できます。
「目に見えない部分こそ、性能が重要」──そんな職人のこだわりで、この高性能ルーフィングを採用しました。


いよいよ新しい屋根材の施工です。
今回はガルバリウム鋼板製の屋根材を採用。
従来のトタンに比べてサビに強く、軽量で長寿命という特徴があります。
施工では、風の影響を考慮してビスの間隔を均等に保ち、接合部にはシーリング材をしっかりと充填して防水性を高めました。
また、熱膨張に対応できるよう、金属板の“遊び”を確保し、気温変化による歪みを防ぐ工夫も施しています。
丁寧に1枚1枚張り合わせ、仕上げの段階で水の流れを最終チェック。
美しく整った屋根が少しずつ姿を現しました。

施工完了後の屋根全景です。
新しいガルバリウム鋼板は、美観だけでなく機能性も抜群。
以前の屋根と比べて段差がなく、雨水の流れもスムーズになりました。
棟板金・水切り・雨押えの細部までしっかり仕上げ、
防水性と耐久性が大幅に向上。
これで長年悩まされていた雨漏りの心配も解消され、
K様からも「安心して冬を迎えられます」とお喜びの声をいただきました。
最後に、施工スタッフが散水テストを行い、雨漏りが完全に止まっていることを確認して完工です。
「見た目もキレイになって気持ちがいい」とお客様にもご満足いただけました。

「雨漏りが止まらず困っていましたが、丁寧に調査してくれて原因を説明してもらえたので安心でした。
葺き替えは大掛かりで迷いましたが、完成後の屋根を見て納得。見違えるほどきれいになりました!」
諏訪市(すわし)は、長野県のほぼ中央に位置し、諏訪湖を中心に自然と歴史が調和した街。
古くから諏訪大社の門前町として栄え、春秋の大祭や御柱祭は全国的にも有名です。
湖畔には温泉や観光施設も多く、四季折々の景色が楽しめます。
一方で、冬の寒さと積雪、昼夜の温度差が大きく、屋根や外壁にとっては過酷な環境。
金属屋根では、凍結や雪の重みで接合部が劣化しやすく、放置すると雨漏りにつながります。
地域に合わせた断熱性・防水性に優れた施工が必要不可欠です。
諏訪市で屋根工事をお考えの方は、地域の気候を熟知した専門店にご相談ください。

街の屋根やさんご紹介
街の屋根やさん松本諏訪平店の実績・ブログ
会社情報
屋根工事メニュー・料金について
屋根工事・屋根リフォームに関する知識
Copyright © 2016-2026 街の屋根やさん All Rights Reserved.