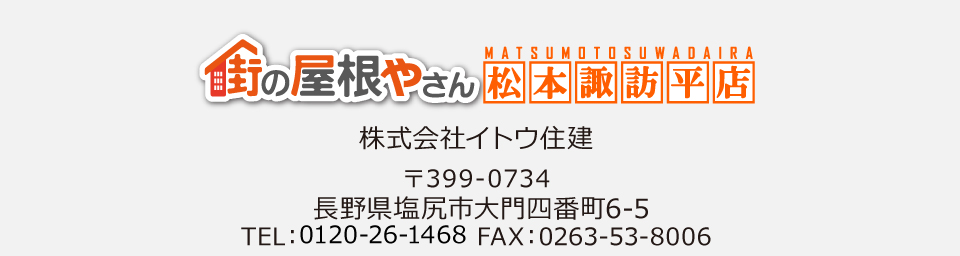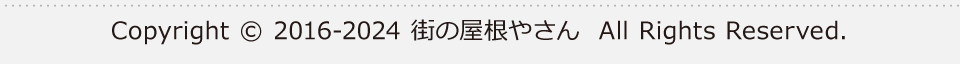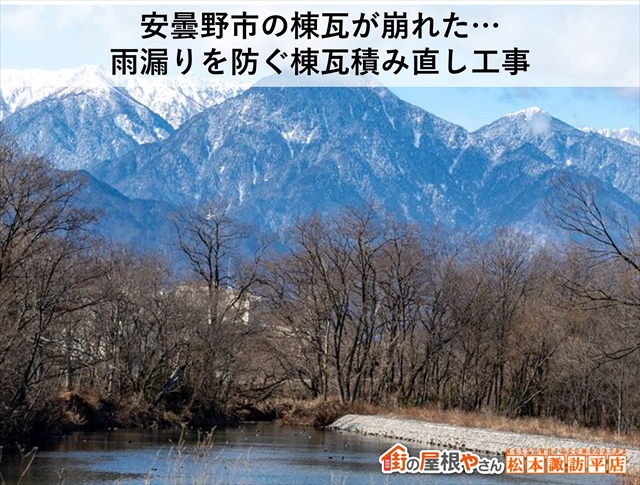
2025.12.03
2025年12月2日 更新 棟瓦崩れは早期対応が安心です 安曇野市のお客様から「屋根の一部が崩れて見える」とご連絡があり、早速現地へ伺いました。瓦屋根は丈夫なように見えても、実は棟(むね)部分は風の影響を受けやすく、少しのズレが雨漏りにつながる“隠れやすい場所&rdq…
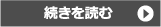

「天井に雨染みが…」「雨の日にポタポタ音がする」――そんな症状に気づいたとき、
屋根全体の劣化よりも、実は棟瓦(むねがわら)のズレが原因になっていることがあります。
今回ご紹介するのは、塩尻市の住宅で発生した雨漏り修繕工事。
天井裏の雨染みをきっかけに現地調査を行い、棟瓦のズレと下地の劣化を確認。
屋根全体の葺き替えではなく、棟部の積み直しだけで雨漏りを完全解消しました。
この記事では、調査の様子・原因の特定・職人の補修手順を、写真付きで詳しくご紹介します。
「うちも似た状況かも…」と思った方は、ぜひ最後までお読みください。

最初の手がかりは、リビングの天井に広がるうっすらとしたシミ。
最初は小さな点でしたが、数か月のうちに輪郭が濃くなり、雨の日にはシミの範囲が拡大していました。
お客様のご不安も強く、「このまま放っておいたら天井が抜けるのでは…」とのご相談を受けて現地調査を実施。
天井の一部を剥がして内部を覗くと、断熱材の裏側がしっとりと濡れており、明らかに雨水が侵入していました。
木下地の梁には黒ずんだ跡があり、長期間にわたって水が滴っていた形跡も。
まずは雨水がどこから入り、どの経路でここに達しているのかを特定するため、さらに上部の構造を追いました。

天井裏をさらに奥まで確認すると、屋根のすぐ裏側にある野地板に、
手のひら大の茶色い雨染みがくっきりと残っていました。
特に棟に近い部分の染みが濃く、雨水が上部から染み出してきているのが分かります。
また、染みのまわりの木材はわずかに腐食が進み、カビ臭も漂っていました。
これは、単なる「結露」や「湿気」ではなく、屋根の上から実際に雨が侵入しているサイン。
屋根の棟部分の真下に位置していたため、
「棟瓦のズレや下地の劣化が主な原因」と判断しました。

屋根の上に上がると、全体の構造は谷と棟が交差する複雑な形状でした。
谷部分は雨水が集まりやすく、棟の重なりや納まりも複数箇所に分かれており、
排水経路が複雑なため、一箇所でもズレがあると雨水が内部に入りやすい構造でした。
特に棟瓦の頂部を確認すると、瓦が少し持ち上がって隙間ができており、
指で押すとわずかに動くほど下地の土が痩せていました。
また、棟の一部では漆喰が剥がれ、雨水が直接入り込める状態。
これらの状況から、棟瓦の積み直しによる補修が最適解と判断しました。


この屋根は、古くから使われている**「土葺き(つちぶき)」工法**でした。
瓦を固定するための粘土質の土が、長年の雨風や凍結によって乾燥・崩れ、
瓦の下に空洞ができていました。
その隙間を伝って雨水が入り、棟下の木部や野地板を濡らしていたのです。
特に棟部分は、屋根の中でも最も雨風を受けやすい場所。
経年で漆喰が剥がれ、土が流出すれば、雨漏りは避けられません。
今回のようなケースでは、棟部を一度解体して積み直すことで、
下地の強化と防水性能の回復が可能です。










工事内容:棟瓦積み直し(部分修繕)
費用目安:1mあたり約1~2万円前後
工期:1〜2日
屋根全体の葺き替えに比べ、低コスト・短工期で雨漏りを止められます。
街の屋根やさんご紹介
街の屋根やさん松本諏訪平店の実績・ブログ
会社情報
屋根工事メニュー・料金について
屋根工事・屋根リフォームに関する知識
Copyright © 2016-2026 街の屋根やさん All Rights Reserved.